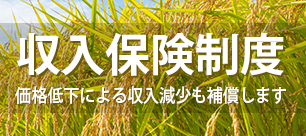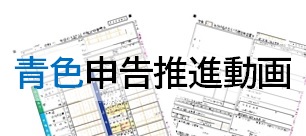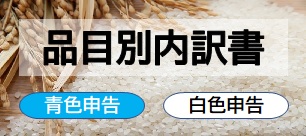情報発信
ワクチン打ってますか?
- 牛の防疫情報
子牛の病気の中でも多いものとしては呼吸器病や下痢症があり、子牛の成長に悪影響を及ぼしてしまいます。これらの病気で獣医師に診療依頼をすることも多いかと思いますが、今回はこれらの治療法ではなく、予防をする「ワクチン」についてお話します。
ワクチンについて
現在製造されている牛用のワクチンはおよそ30種類あり、呼吸器病予防・消化器病予防・異常産予防・乳房炎予防など、さまざまな病気を予防するワクチンが販売されており「生ワクチン」と「不活化ワクチン」があります。
【生ワクチン】
生ワクチンとは、ウイルス株や細菌株が生きているもの(感染性があるもの)をいい、病原体が体内で増殖することにより免疫が誘導されます。生ワクチンは不活化ワクチンよりも効果が高く、免疫の持続時間も長い傾向にあります。効果面においてもメリットの大きい生ワクチンですが、体内で増えた病原体が対外に排出され、同居牛に感染する可能性もわずかながらあるなどのデメリットもあります。
【不活化ワクチン】
不活化ワクチンとは、死んだ状態の病原菌、あるいは病原体の一部のみを含んだワクチンであり、感染性はないものの、一般的に生ワクチンと比較して効果が弱く免疫の持続期間が短い傾向にあり、十分な免疫を得るためには原則として2回以上の摂取が必要です。
生ワクチンと不活化ワクチンどちらもそれぞれメリット・デメリットがあるため、農場の状況や使用目的に応じて使い分ける必要があります。
また、使用に際しては注意しなければならないこともあります。例えば、BVD(牛ウイルス性下痢)に対する生ワクチン株は、胎子に感染し流産したり持続感染牛を生じさせることから、BVD生ワクチンを含む混合生ワクチンは「妊娠牛、交配後間がないもの又は3週間以内に種付けを予定している牛には接種しないこと」とされています。
現場でよく使われるワクチン
現在、畜産現場でよく使用されているものには、呼吸器病予防ワクチン・下痢症予防ワクチンがあります。
呼吸器予防ワクチン
製品によって種類や内容は異なりますが、主に牛伝染性気管炎ウイルス・牛ウイルス性下痢ウイルス・牛パラインフルエンザウイルス・牛RSウイルス・牛アデノウイルスなどの呼吸器病感染症の予防、あるいは呼吸器症状に対する予防を目的として使用します。簡単に説明すると風邪予防です。主に親からの移行抗体が消失する3カ月齢以降の子牛に対して使用します。
また、市場によっては接種が必須となっているため、牛を出荷するために出荷直前だけ打つ方もいますが、多頭飼育の牛舎では呼吸器病はあっという間に蔓延し、治療が追い付かないこともありますので、子牛の時期にしっかりと接種し、その後半年から1年おきに追加接種することをお勧めします。
下痢症予防ワクチン
下痢症予防ワクチンは、一般的なワクチンと異なり、妊娠牛の分娩予定日の1.5カ月前および0.5カ月前に接種することで母牛を免疫し、その初乳を飲ませた産子の牛ロタウイルス病・牛コロナウイルス病および牛の大腸菌症を予防するというものです。産まれたての子牛で下痢が多発してしまうという方にはぜひお勧めしたいワクチンです。
ワクチンって効くの?
診療中に「ワクチンって効くの?」「ワクチン打ったのになぜ調子が悪くなるの?」など聞かれることがあります。
ワクチンの効能効果は一般的には病気の予防ですが、ワクチンを接種することで完全に病気を予防できるわけではありません。しかし、接種することで発症する牛の頭数は確実に減り、発症しても重篤にならないことが多くなります。
経験上、子牛の下痢が多発していた和牛繁殖農家では、母牛に下痢症予防ワクチンの接種を徹底してもらうことで、1年後には畜主の方も実感できるほど下痢症状を呈する子牛の頭数が減少、あるいは下痢をしても重篤化することがほとんどなくなり、大変満足していただけました。
最後に
畜産現場での感染症の発生は、死亡や廃用のような直接的な損害や治療コスト増大、増体重の減少など、生産性へ大きく影響を及ぼします。それぞれのワクチンの特徴を理解した上で適正に使用し、病気を予防するだけでなく生産性を上げることができますので、ワクチン接種をしてみませんか?
興味がある方は、一度お近くの獣医師にご相談ください。
道央統括センター上川中央支所
上川中央家畜診療所
獣医師 中山 真吾



.jpg)
.jpg)